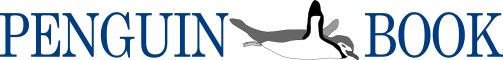アデリーペンギンの特徴
アデリーペンギンは、「Suicaペンギンのキャラクターになっている」といえばイメージが湧くでしょう。
目の周囲にある白色のアイリングと、白黒のツートンカラーが特徴的。
また表情が豊かなのも、キャラクターにしやすい特徴でもあります。
アデリーペンギンは、日本人がとても親しみやすいペンギンなのです。
アデリーペンギンの写真


アデリーペンギンの生態
基本情報
・種小名アデリアエ (adeliae) は「アデリーさんの」という意味。南極大陸のアデリーランドという島名と同様に、フランスの南極探検家デュモン・デュルビル体長の婦人の名前にちなんで命名された。
【最初の繁殖時期】早い個体では、メスが3歳、オスが4歳
【寿命】約20年
【天敵】ヒョウアザラシ、オオトウゾクカモメ
生息地
アデリーペンギンは、南極大陸とその沿岸の周囲にある島々に生息している。
南極大陸以外での繁殖地は、サウス・シェットランド諸島、サウス・サンドウィッチ諸島、ブーベ島、スコット島、バレニー諸島、ピーター1世島などがある。
繁殖は、南極大陸の海岸と、周辺の島の海から容易に近づける露岩(夏期、雪や氷が溶けて地面が露出する場所)上で行う。
分散
放浪個体は、亜南極の島々、ニュージーランド、オーストラリアまでやってくる。
外観
冠羽
後頭部に冠羽があり、ディスプレー(誇示行動)のときにはこの冠羽が立ち、頭部の輪郭が角張る。
参考:ペンギンズの隊長(映画「マダガスカル」に出演のキャラクター)
目
目は茶色。目の周囲の独自の白色のアイリング(白い輪)がある。
フリッパーの長さ
19.2 cm オス | 18.9 cm メス
くちばしの長さ
4.0 cm オス | 3.6 cm メス
黒色のくちばしは短く、寒さから守るために羽毛で覆われている。
体重
3.7〜6.0kg
[繁殖地への帰還時] 5.3 kg オス | 4.7 kg メス
[産後] 4.3 kg オス | 3.8 kg メス
ヒナ(赤ちゃん)
ヒナの羽毛は、密でふわふわした濃い灰色。巣立ちヒナは、成鳥で見られるような白いアイリングがない。
習性と行動
採餌
抱卵期のあいだは長期間の採餌に出かける。餌が豊富な流氷のない、流氷帯の沖合の海域まで出かけることがある。
ヒナに餌を与える育雛期では、採餌を短時間かつ近場で行う。
上陸
時速25kmのイルカ泳ぎで氷縁まで近づくと、水中を高速で接近し、海面から2mを超す氷の上に飛び上がる。頑丈な足の爪で氷を掴み、体を固定する。
移動
内陸の繁殖コロニーまで徒歩で移動する。途中、時速4kmの移動速度のトボガンで移動することによってエネルギーを節約する。
性格
アデリーペンギンは、臆病なジェンツーペンギンと違う。人間が接近しても逃げ出さないで立っている。またオオトウゾクカモメに対しても攻撃的に行動する。
ディスプレー
アデリーペンギンのディスプレーはよく研究されている。威嚇する際は頭の羽毛を立てる仕草がよく見られる。「直接にらみ」「固定された横にらみ」「かがみこみ」などがある。
巣作り
巣は、海岸地帯の地肌が露出している場所に小石を積み上げて作る。
より高く積み上げた巣の方が繁殖の成功する可能性が高い。
巣は、クチバシでつつき合えるくらいに隣の近くに作られる。
繁殖地に10万ものペンギンが集まると、巣作りに使える小石はたちまち不足してしまう。
近くの巣や放棄された巣から石を盗んでくる。この盗む行為は頻繁に行われている。
換羽
成長と巣立ちのヒナは、海岸、海氷上、氷山の物陰で、3週間かけて換羽する。
繁殖
・(繁殖期)10〜2月までの短期間。
生まれた繁殖地に戻ってくる。内陸に100km以上移動してコロニーに到着する。
コロニーには最大50万羽もの個体がいる。
ツガイの絆は非常に強い。アデリーペンギンにとって巣は再会の場である。
・(産卵期)11〜12月初旬。1ヶ月以上にわたる。
コロニー到着後12日で産卵が開始。1回の繁殖で2個の卵を産む。
つがいの両方とも約3週間の絶食をしている。
・(抱卵期)
オスが最初の抱卵を担当する。コロニー到着時のオスの体重はメスよりも重い。オスは、メスが採餌に海へ行っている間、4〜6週間の絶食を耐えるだけの体力を持っている。
強烈な吹雪になるとアデリーペンギンは雪に埋もれてしまうが、卵を抱卵し続ける。
アデリーペンギンは、足の上で抱卵する点が皇帝ペンギンとキングペンギンに似ているが、直立して抱卵しない点が異なる。他の種のペンギン同様に、卵の上にかがみ込んだ腹ばいの姿勢で、卵を覆うようにする。
・(クレイシ期)
孵化後も、22日間は、親鳥が交代で世話をする。
ヒナは、3週間ほどで綿羽が生えかわり、クレイシを形成する。クレイシは5〜20羽の小規模からなる。
・(巣立ち)
気候が安定していて、餌が豊富な年には、ヒナが2匹育つ。
ヒナは、約7〜8週間でコロニーから巣立ちする。
生息状況
・準危急種 (2012年 レッドリスト)
地球温暖化によって個体数が減っている繁殖地もある。
・推定個体数 2,610,000 繁殖つがい 10,000,000 幼鳥 (Croxall 1985年 from 国立極地研究所)
アデリーペンギンの関連動画
アデリーペンギンに出会える水族館
アドベンチャーワールド(和歌山県)
名古屋港水族館(愛知)
横浜・八景島シーパラダイス(神奈川県)